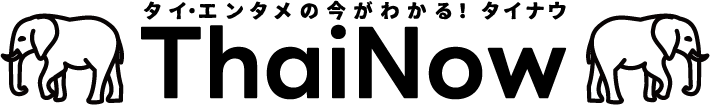―――今回の楽曲は、これまでのScrubbのイメージとは真逆ともいえる激しいサウンドですが、ユニバーサル所属後の第一弾シングルとして、この曲調を選んだ理由を教えてください。
ボール:
(笑)実際のところ、「この曲で変化を見せよう」とか「従来と違う方向にしよう」といった意図は最初はまったくなかったんです。ただ、せっかく機会があるなら、これまであまりやってこなかったことに挑戦したいと思って、リズムが楽しくて、少しアグレッシブさのあるロック――そういうモードは僕たちにはあまりなかったので、やってみようと。
実際に作ってみたら結果にとても満足できて、新しいEPアルバムの制作も始まっていて、“新しい家=ユニバーサル・ミュージック・タイランド”でもあるし、この曲は、楽しさ・新しさ・新章の始まり(ニュー・チャプター)という意味を象徴していると感じたんです。だからこの曲を最初の作品として選びました。
―――曲調は今までのScrubbとは大きく異なりますが、ムアイさんの声が入ることで「Scrubbらしさ」を感じることができます。今回、歌い方などで普段と違う工夫をされた部分はありますか?
ムアイ:
はい。この曲は結構準備が必要でした。重い曲なので。実際のところ、歌う前にしっかりウォームアップしないといけないです。
コツといえば、ライブでは序盤に歌うようにすること。体力のあるうちに!(笑)
それに、実はけっこう難しい曲でもあって、音域が高いんです。だから、しっかり準備して臨むようにしています。
―――普段はボールさんがムアイさんの歌詞にメロディを乗せることが多いですが、今回はボールさんが先に音楽を作り始めたそうですね。以前、カシオペアやX JAPANから影響を受けたと話されていましたが、このようなスタイルの曲を前からやりたいと思っていたのですか?
ボール:
前に日本で仕事をしたときのインタビューでも話しましたが、子どもの頃はCasiopea(カシオペア)を聴いて育ち、ある時期はX JAPANの大ファンでした。
まとめて言うと、僕が音楽を聴いたり演奏したりするインスピレーションの一部は、日常的に日本の音楽から得ているんです。だから日本のアーティストや作品をずっと追いかけてきました。
そして、この曲の骨組みができたとき、最初の感覚として「Ichikaさん(=日本のギタリスト)とぜひ一緒にやりたい」と強く思ったんです。以前に別の仕事でお会いしたことがあって、僕らの音はロック寄りなので、Ichikaさんのギターが入ると“アジア・サウンド”“アジアのバイブ”の象徴のような存在感が出て、Ichikaさんならではのスムーズさや甘さが、Hippoという曲のいくつかのパートをより丸みを帯びて美しくしてくれるんです。
つまり、日本の音楽はずっと僕たちのインスピレーションの源であり続けてきました。
この曲は、僕たちがさまざまなロックバンドと共に成長してきた、その延長線上にある1曲でもあります。
―――Ichikaさんはタッピングやクリーントーンによる独自の伴奏が特徴的ですが、今回は大胆にギターソロでフィーチャーされています。これはどちらのアイデア/リクエストによるものですか?
ボール:
この曲のデモを作り終えたときに、「Ichikaに参加してもらいたい」と思ったんです。ロックのサウンドと、彼のメロディーの美しさや技巧的なプレイ、一見すると相反するようで、でも一緒に存在できるようなその“違い”がきっと面白い化学反応を生むと思いました。それがIchikaのファンにも、僕たちのファンにも新鮮な驚きを与えるはずだと感じたんです。
Ichika:
デモを聴いたときに、ラストの部分でギターソロをかましたいってBallに提案したら彼も同じように思ってたみたいです。
―――Ichikaさんは「ドリーム・シアター」などプログレッシブ・ロックの影響を語ってこられました。今回の楽曲にはヘヴィでプログレッシブな要素も感じられますが、Ichikaさんご自身はどの部分に魅力を感じましたか?
Ichika:
この曲のギターリフがかっこよすぎてとてもテンションが上がったのを覚えてます。
―――この曲は力強く先鋭的でありながら、フックではポップなハーモニーとボーカルが美しく調和しています。この“アヴァンギャルド”と“ポップ”の融合において、ムアイさんとボールさんは、バランスや細部はどのように意識しましたか?
ボール:
曲の中のポップな要素のことですよね?
――そうです。2つの要素をどうバランスさせたのですか?
ボール:
考える段階で、もし楽器の演奏だけを基準にリフや構成を考えてしまうと、まだメロディがない状態でも仕上がりの可能性が何通りも出てくるんです。つまり、どう“デザイン”するかによって結果が大きく変わる。ただ、僕たちは基本的にインディーロックをやっているので、この曲が他より少し“重く”聴こえるにしても、どこかに自分たちらしいつながりを残したかったんです。そこで、聴きやすく耳に残るメロディを入れて、がなり立てたり、怒鳴ったりはしないようにしました。それがロックの一つの魅力でもあると思っていて――リズムがあり、楽しいテンポがあり、その上で、どんな表現や物語やメロディをどうデザインするかで曲の方向性が決まる。だから僕らは、メロディや歌詞の部分で“自分たちらしさ”を残して、歌詞もあまりシリアスになりすぎないようにしています。